パソコンサポート 京都市 パソコンサポート 右京区 パソコンサポート 御室 パソコン・ノート・スマートフォン・なんでもお任せください。
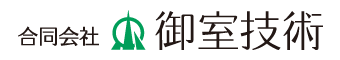 |
|---|
|
ブログ本文検索
検索エンジン
新着日記
JPYC (01/07)
ネットワークエンジニアとAIと士業と (12/24)
仕事をしながら見える5年後 (12/24)
お詫び (12/18)
AI推論とnVidia B200とAMD MI355X (12/16) カテゴリー
カレンダー
年月分類
ユーザプロフ
システム
|
2013-01-31 Thu [ 技術屋の独り言 ]
by su
またFUJITSUがやってくれました。http://pr.fujitsu.com/jp/news/2013/01/29-1.html 理論: TCP:△△▲▲△▲▲△▲▲△▲▲△▲▲△ UDP:△△▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲ TCPは確認するため、△(無通信時間)が単純ロスになります。 だからTCPで通信されるデータは、到達を保証しています。 UDPは相手がオーバーフロー中でも容赦なく問答無用で送ります。 だからUDPは、データの到達を保証しません。 現状: TCPで転送するデータの長さが以下の状態で TCP:△△△▲▲△▲▲△▲▲△▲▲△▲▲△▲▲△▲▲△△ TCP:△△△▲▲△▲▲△▲▲△▲▲(ここで切断されると) 最初からやり直しになります。 上記のようになる確率は、現状の通信時間の半分以上です。 TCP経由でウィルスが送信された場合はワザとこの理論を応用し、 何度もリトライが入ります。その度にウィルス対策ソフトが 何度も同じウィルスを検出します。 ウィルス対策ソフトでウィルスを検出してみるとわかりますが、 同じ名前のウィルスが3つも4つも紐付けされるのはそのため。 誰もが考えられそうな高速化は、TCPが混んでる時にUDPを使う。 ですが…状況に応じてロードするプロトコルを切り替えてては、 制御系に大幅な負荷がかかりますし、ネットワーク設備資源より 制御系設備資源の方が費用も高く、経年劣化も高いので無理です。 また受け側コンソール(クライアント)がTCPからUDPに切替状態で デッドロックがかかれば、再起動しなければリンクダウンしたまま。 以上から、UDPはあくまでサーバ用、利用するとは考えにくい。 次に考えられるのは、 ロスが出た(確率6割)時にデータ長(DLF)と巡回冗長(CRC)を監視して、 そこから再接続する技術をソフトウエアで実現したのかな??
| 09:42 | comments (x) | △ |
|
|---|
御室技術 |
企業情報お問い合わせ |
関連事業 |
トピックスリンク |
Copyright © 2010 - 2013 OmuroGijyutsu Co.,Ltd. All Rights Reserved.